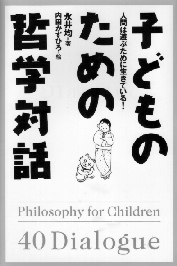哲学の泉通信2000年6月20日第1巻第1号 (通巻1号)発行者:千葉県立泉高等学校 片岡 勝規倫理授業用プリント。不定期刊行の予定の倫理ニュースレター。A4の両面刷りで2ページで配布している。最近は授業でビデオばかり見せていて板書も少ないのでこのようなものを作り始めた。 Contents(本号のハイライト) 1 哲学を手に入れよう! ― Get philosophy !おそらく,あなたも「哲学」という言葉に対して,難解そうな印象や近寄りがたい雰囲気を感じるのではないだろうか? 哲学というと,ごく簡単なことをわざと難しい言葉で表現して優越感に浸るイヤミな学問のように思われていることがある。もし,それが哲学の本当の姿ならば,多くの人にとってこの学問は学ぶ価値のないものだろう。ましてや高校生にはまったく必要のないものだろう。 この「哲学の泉通信」では,哲学を学問の一分野としてだけではなく,もっと広い意味でとらえたいと思う。よくいわれることだが,哲学=philosophy(フィロソフィ)の語源は,古代ギリシア語の「知」と「愛する」 である。だから,ここでは何かについて疑問に思ったり,調べてみたり,考えてみたり,話してみたり,書いてみたり,そんな精神活動をみんなまとめて「哲学」であると考えたい。そういう意味で哲学とは僕らにとっても学ぶに値する学問だ。 2500年も前から哲学の歴史は続いているのだから,きっとあなたが考えていることと同じようなことを考えていた人はいるはずだ。また,考え方や表現の方法についても,古くから伝わるいろいろな積み重ねがある。思考や探究や表現の方法を,携帯電話やパソコンを買う感覚で手に入れてみること。つまり,哲学を手に入れることを,私はこのニュースレターを通して皆さんにお薦めしたいと考えている。 2 哲学ってなんだろう?違和感を大切にする 毎日の生活の中で,「何か違うぞ」というような気持ちになることはないだろうか。理由はよく分からないけれども納得できないことがあったり,頭の中が「イライラモヤモヤ」して,考えがまとまらないようなときだ。そんなときは他のことで気をまぎらせたり忘れたりするのが,精神衛生上はよいのかもしれない。しかし,違和感を忘れるのではなく,そこから出発するのが哲学の思考だ。 そもそも,違和感とは自分と世界とのズレの意識だ。他人の生き方や考え方と自分の生き方や考え方のズレ。世間の常識と自分の常識のズレ。このようなズレは確かにある。同じ人間は2人いないという意味において,そのズレこそが他人と違う自分らしさ,つまり個性なのだ。そんなズレに対して,わたしたちは何ができるのだろうか。 まず考えられるのは違和感に対して,何が違っているのか,なぜ違っているのかを確かめることだ。自分にとって何が違っていて(No),何が合っている(Yes)なのかをハッキリさせる。つまり,自分にとっての真理を探し求めることができるということだ。そして,それが哲学であるためには,論理的に(感情的にではなく)思考しているか,他人の考えを参考にしているか(ひとりよがりではなく),ということが大切になる。世の中に対してスネてみても,独善的な考えを持ってみても,それは哲学の名には値しないだろう。 そして,その次の段階で自分と世界のズレにどう折り合いをつけるかということが問題となる。違和感を忘れるのでも否定するのでもなく,それを抱えながら現実にどうやって生きていくかということだ。自分にとってのNoが,他人にとってのYesであることはよくあることだ。そこをどう乗り越えるのかということも,立派な哲学のテーマである。 3 哲学の驚き(1)プラトンとマトリックス 1999年にヒットした映画『マトリックス』の魅力は,主演のキアヌ・リーブスの特撮アクションやCGだけではなく,その奇抜な世界設定にもあったと思う。映画の中の1999年,人々がリアル(現実)であると考えていることは,じつはすべて仮象(仮のすがた)であるということが明らかになる。そして,現実には今は2199年であり,人間はコンピュータのエネルギーとなるべく液体の中で栽培されている。人工知能につながれた人間が真実だと思い込んでいることのすべてはコンピュータの作り出した仮想現実の世界(=マトリックス)の中のできごとに過ぎない。人間はコンピュータが作った夢を現実と思い込まされてカプセルの中に植物のように生きている。コンピュータに栽培されている人間を救おうとするのがキアヌ・リーブス扮するネオだった。 この映画の基本設定の中には,「目に見えるものがリアル(現実)である」という考えは単なる思い込みに過ぎないという発想がある。そしてその発想は古代ギリシア哲学の考え方にさかのぼることができる。古代ギリシア語のアレーテイアという言葉は「真理」を意味するが,もともとは隠されたものを打ち破るという意味だった。そして,今から約2500年前のギリシアの哲学者プラトンは,著作『国家』の中で人間の本性について次のような比喩を用いて説明している。 人間たちは子供の頃から洞窟の中で手足も首も縛られた状態にいる。そこから動くことができない彼らが見ているのは,壁に映った影だけである。光は彼らの背中側から降り注ぎ,実物も背後にあって直接見ることができない。もちろん縛られた人間たちはそれを知らずに壁に映った影をリアル(現実)だと信じ込んでいる。このような比喩――まるでコンピュータ抜きのマトリックスの世界――を使って,プラトンは視覚や聴覚などの感覚を超えた真理が存在することを主張した。 たとえば,わたしたちが見る美しいバラの花。しかし,花が枯れてしまえば「美」はなくなってしまうように,わたしたちの経験する「美しさ」は一時的で不完全なものでしかない。完全な「美」,本当の「美」は日常的な経験世界とは違う世界に真実に存在する。それをプラトンは「美のイデア」と呼んだ。このようなイデアの世界を人間は感覚的に知ることはできないが,純粋な思考によって認識することはできる。これこそが,永遠に不変で完全な真の実在の世界であると考えた。直接目で見たり肌で感じたりする感覚よりも,理性の働きによる論理的な思考の方が確実で真理に近いという,西洋の合理主義の原点がここにある。 すべてが「見えるまま」に素朴に実在しているという常識を,情報技術が簡単に覆してしまえる今,「何がリアルなのか?」という問いは,2500年前とは違った意味をもつ問いになってしまっているのではないだろうか。 4 ブックガイド 『こどものための哲学対話』 (著:永井均,講談社,¥1,000)
「ぼく:哲学って,それなに? ペネトレ:つまり・・・・・,自分で勝手にやる学問のことさ。 ぼく:自分で勝手にやるって,独学って意味? ペネトレ:ちがうよ。すでにある学問を一人で勉強していくんじゃなくて,問いそのものを自分でたてて,自分のやりかたで,勝手に考えていく学問のことを,哲学っていうんだよ。」 ペネトレは本当に勝手に,「じつは地球は丸くない」とか「くじらは魚だ」という議論を展開する。それを読むと,いかに自分が常識にとらわれているかということを気付かされる。目からうろこが落ちる本だ。 5 雑感 【さまよえる倫理の基盤】人は,なぜ悪いことではなく,正しいことを行わなければならないのだろうか。極端な例で言うならば,なぜ人は人を殺してはいけないのだろうか。 たとえば,キリスト教徒にとっての倫理の基盤はイエスの言葉や行いである。神を愛し,自分と同じように隣人を愛するという掟からすれば,人を殺すということは明らかに間違った,禁じられるべき行為である。 これまでの日本人にとっての倫理的な行動の基盤は,人目と世間と村八分だった。世間様に対して恥ずかしくないおこないをしなければ,ヨソ様に相手をしてもらえなくなるという考え。お母さんの子供に対する「〜さんにしかられますよ」というしつけ方が,その考え方をしっかりと植え付けてきた。 しかし,そのような倫理基盤は,他人の目を一切気にせず,自己中心的に生きるならば,まったく意味をなさなくなってしまう。 さまよえる日本の倫理基盤はどこを目指せばよいのだろうか。少なくとも,教育勅語ではないことだけは確かなのだが… 片岡の倫理・哲学教材研究へ戻る ページのトップへ戻る |